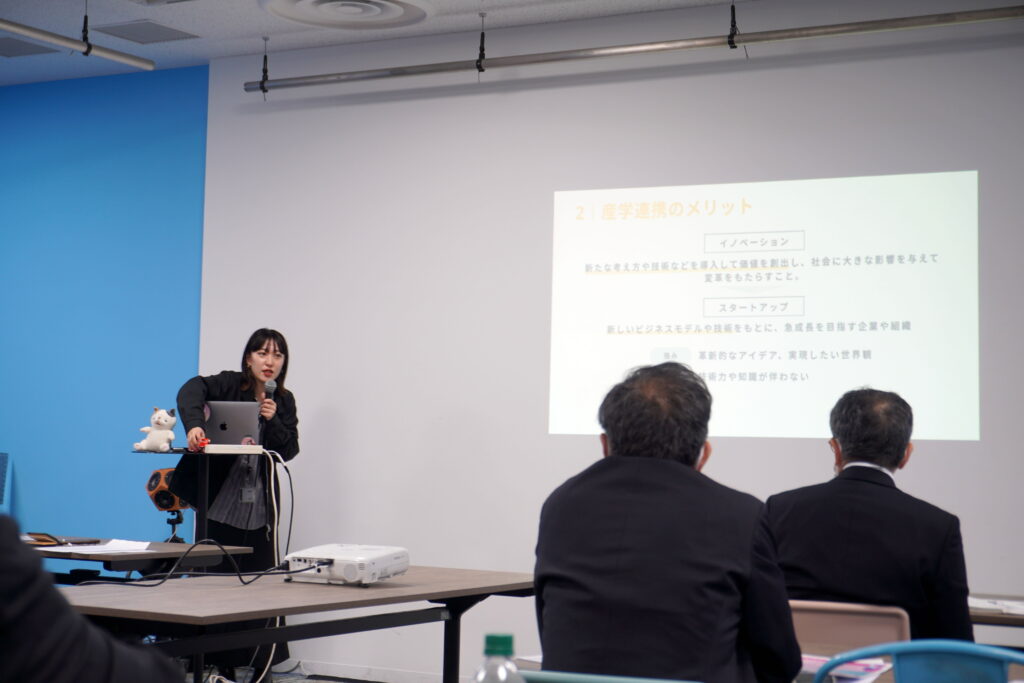イベント・講演会
【3/28(金)】スタートアップと大学の産学連携促進イベント「ものづくりスタートアップに向けた産学連携のススメ with TIB FAB」を実施いたしました
はじめに
当社では、東京都による「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」の令和6年度採択者として、スタートアップと大学の産学連携の促進に向けてさまざまな取り組みを行っています。
その一環として、2025年3月28日、Tokyo Innovation Base(TIB) 2F SABAにて「ものづくりスタートアップに向けた産学連携のススメ with TIB FAB」を開催いたしました。そのイベントの様子をレポートします!🎉
イベント概要
本イベントは、ものづくりスタートアップの支援に取り組むTIB FABとの共催により、技術力向上や開発資金の確保、実証フィールドの確保といった課題を抱える、ものづくりスタートアップを対象に開催されました。
当日は、大学との連携に関心が高く、実際に大学との連携を通じてプロダクトやサービスの向上に向けたヒントを得たいという、ものづくりスタートアップの方々などが多数集まり、以下のテーマで登壇者がお話をされました。
講演内容
1. ものづくりスタートアップ目線から考える、産学連携に取り組む可能性とメリット、スタートアップ×大学 産学連携促進プログラムのご紹介
キャンパスクリエイトでは日本全国を対象に産学連携を推進しており、80校の大学と連携して共同研究のマッチングや企画、実用化支援などを行っています。そんな当社に寄せられる、ものづくり分野での産学連携に関する問合せには、以下のようなものがあります。
- 新製品開発・・・研究シーズを活用して製品化したい
- 自社製品の改良・・・センサーの検出精度を向上させたい、装置の複雑な初期設定を自動化したい
- 作業現場に関する相談・・・工場設備の稼働率の見える化、加工作業の自動化、生産工程のシミュレーション
- 評価・・・自社製品の感性評価、製品パッケージの評価、製品評価方法の確立、大学の測定機器の活用
- 顧客からの要求への対応
- 社員教育・・・プレス加工など専門技術に関する社員向け研修、AI導入研修、管理職研修
- 新事業検討・・・アイデア段階での研究者への相談
実際に大学と連携するメリットには以下のようなものがあり、特に1)~4)は多くの企業に役立つものといえます。
- 研究成果を活用できる。研究者の知見からのノウハウやアドバイスが有効
- 大学の評価装置など、設備が利用しやすい
- 学生が研究に参加する
- 事業化の際のブランディングとしても有効
- 大学が実施する企業向けイベントなどに参加しやすい
- 大学発スタートアップとの交流
一方、産学連携する際の流れと、各段階における課題には、以下のようなものがあります。
- 課題抽出:企業における現状の課題を整理、新規事業の検討など → 検討するための情報不足、社内での人手不足など
- 企画検討:実施内容の検討にあたり、外部との連携を検討 → どの大学でどのような研究をしているか分からない。研究紹介を見ても、自社課題が解決できるか判断できない
- 連携調整:連携先と「実施内容」「スケジュール」「予算」「アウトプット」について相談 → 企業と大学とで「当たり前」が異なるので、実施内容のすり合わせが必要。契約条件のすり合わせが困難な場合も
- 事業検証:共同研究を実施する傍らで、事業化に向けた検討を進める → 共同研究での研究者や大学との密な連携が必要。意識のズレが発生する場合も。知財の取り扱いや研究発表などでも大学との協議が必要
- 事業化に向けて:試作開発やマーケティング、量産計画、外資金の獲得などを駆使して事業計画を推進 → 事業化に向けては多くの検討事項が残っており、自社だけでは取り組めない場合が多い。新たな協業先を模索する必要も
このような状況に対し、産学連携を成功させるポイントとして、研究者への相談方法(事前調査のし方、大学の産学連携部門の活用など)や、連携先の研究室と事前検証を行うこと(提案方法、計画書のまとめ方)、そして共同研究を進めるうえで協議が必要な事項などが紹介されました。
また、産学連携の動向について、大学における民間企業からの研究資金などの受入額は基本的に右肩上がりを続けてきました。民間企業との共同研究における受入額規模別の件数では300万円以下が8割で、100万円以下でも連携することは多くなっています。一方、研究費の規模別受入額では1件あたり1000万円以上が6割となっており、二分化しています。大学や研究室によって環境は異なるため、産学連携を考えるときには留意が必要です。
他国の例を見ると、ドイツではスタートアップの半数が大学や研究機関と連携しており、支援を受けたスタートアップの約9割がその結果を肯定的に評価しています。日本政府も骨太の方針で大学と企業を橋渡しして民間投資を呼び込む体制を強化するとし、特許庁はオープンイノベーションのためのMANNER BOOKを作成。文科省も、企業とスタートアップの連携を支援する大学を対象とした事業を行うなど、大学とスタートアップによる産学連携が本格化しようとしています。
当社としても、東京都のスタートアップエコシステムにおいてスタートアップが大学を積極的に活用していくのを当たり前にすることを目指しています。本日のイベントはTIB FABと共催していますが、TIB FABがさまざまな企業にこの場を開放してスタートアップを支援されるなかで、大学ももっと活用いただきたいと思っています。
また、当社では「スタートアップ×大学との産学連携促進プログラム」で採択企業に、連携先研究者の調査・マッチングから連携計画のプランニング、事業化、広報までワンストップで支援を実施中(2026年3月末まで)。そのほか、大学との連携に興味があったり、すでに取り組んでいる産学連携を加速させたいといったスタートアップからの相談に対応する産学連携相談窓口「ACADEMIC PARTNERSHIP DESK」も受け付ています(受付期間2026年2月13日まで)。
そして、当社が支援した産官学連携の取り組み事例として、ANA発スタートアップのavatarin社が大田区役所本庁舎にてアバターロボット「newme」を活用して遠隔区民案内サービスを実施した案件を紹介。最後に、TIB FABとの関連性をふまえて、ものづくり分野における産学連携の事例を7件ほど紹介して、締めくくられました。
2. 芝浦工業大学における産学連携の取り組みと、ものづくり・デザイン分野の研究者紹介
芝浦工業大学では、大学の持つ知の資源と地域のニーズを結びつける「知と地の創造拠点」として、自治体や企業などとの共同研究を推進。受託・共同研究の件数は年間200~300件もあり、金額も近年増えているといいます。産学連携の対象領域は理工系全分野で、機械、電気電子、情報、建築、デザイン工学、化学・生命科学など、幅広く網羅しています。手続きについては、産学連携コーディネーターやURA(リサーチ・アドミニストレーター)が、研究契約や知的財産管理など煩雑なものについてサポートしているとのこと。
また、同学が考えるスタートアップにとっての産学連携のメリットとして、以下のような点が挙げられました。
- 大学が有する多様な研究分野と先端的技術にアクセスし、自社の製品・サービスに活かせる。
- 大学の研究者や学生から客観的視点や新しい発想が得られる。
- 大学との研究成果で学会発表などにより、社会的信頼につながる。
- 公的助成、補助金を活用できるケースがある。
- 学生との協働で採用につながる可能性もあり得る、など。
その後、ものづくり・デザイン分野の研究者を、研究室検索サイトの使い方を示しながら紹介。そして、連携の具体例も複数案件が紹介されて、最後に問い合わせ先が示されました。
3. エモーショナルデザインを生かしたものづくり
これからの商品は機能を果たすだけでなく、使っている人が気持ちよく使えたり、満足感や愛着を持てることが大事だといいます。そこで、橋田教授のエモーショナルデザイン研究室では感性工学を用いて魅力の要素を追求し、その分析結果をものづくりに取り入れることに取り組んでいるとのこと。
実際にエモーショナルデザインを行うには、形や色、材料、テクスチャーといった造形の要素ごとの効果を確認して、対象物に施していきます。そのため、まず消費者の感覚や価値観を確認できるよう、アンケートを実施するなどして、それぞれの要素がどのように人の気持ちに作用するかを調べます。一般的に企業では次々と商品開発が行われるため、こうした研究はあまりできません。これをしっかり行えるのは大学ならではといえます。そうして、目標とする製品のイメージを言語化して、ものづくりのデザインコンセプトとしていくとのことでした。
そして実際に橋田教授が手がけた、キッチントレイのエモーショナルデザイン事例がプロセスに沿って、使用するフォーマットなどと合わせて紹介されました。
4. TIB FABが考えるスタートアップと大学の産学連携のメリット
TIB FABを運営しているのは、DMM.comが社会貢献としてスタートアップ支援に取り組む法人である(一社)DMM.make TOKYOです。同社は秋葉原で9年半、ハードウェアのものづくりができるコワーキングスペースを運営してきました。その実績を活かしてTIB FABではプロトタイプの製作やプロダクトの試作が可能な実証フィールドを運営し、ものづくりスタートアップの拠点としてハードウェア開発に必要な設備や技術ノウハウ、ネットワークを提供しています。
そしてTIB FABとしては産学連携によって、スタートアップには難しいといわれるハードウェアに誰もが挑戦しやすく、ものを生み出していける場所になっていきたいといいます。革新的なアイデアや実現したい世界観があっても、スタートアップでは技術力や知識が伴わないといったときに、大学と連携することでイノベーションを起こせると考え、互いの強みを生かした連携によって開発のハードルを下げていきたいとのことで、イベントが締めくくられました。