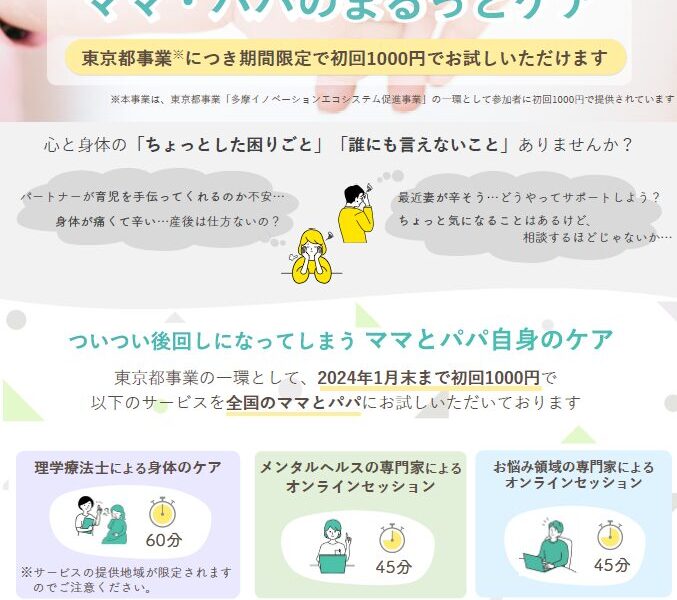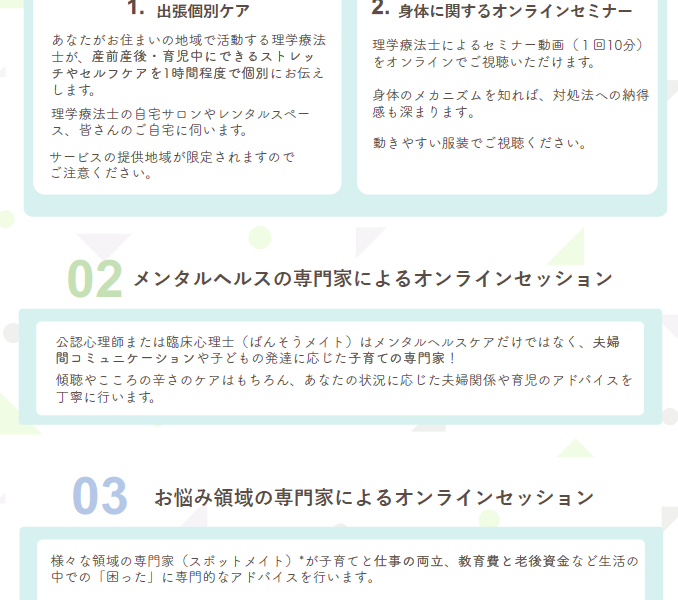全国の取り組み事例
メンタル不調ゼロをめざして─大学発スタートアップ BANSO COの軌跡
はじめに
既存サービスでは解決できない課題や、社会課題解決に取り組みたいという企業の「思い」と大学の専門的な知見を結びつけ、新たな価値を生み出す産学連携。その形はさまざまですが、近年では大学の研究室で生まれた課題意識や専門知識を核とする「大学発スタートアップ」も、社会実装を加速させる一つの形として存在感を増しています。
今回紹介する株式会社BANSO-CO(以下、同社)もまた、そうした大学発のスタートアップの一つです。東京科学大学(旧・東京医科歯科大学)発スタートアップである同社は、代表の鶴田桂子さんが経験したメンタルの不調を原体験に、共同創業者である伊角彩さん、土井理美さんが学術的に蓄積してきた知見と現場での気づきが重なることで生まれました。
本記事では、創業メンバーの言葉を通して、研究シーズが試行錯誤を経て事業へ結実していくプロセスと、産学連携が生む可能性をひも解きます。
心のケアを、もっと気軽に
同社では、主に次の三つのサービスを展開しています。まず、企業・団体の従業員等が利用できる法人向けのオンライン相談窓口。次に、個人のお客様が直接利用できるカウンセリングサービス。そして、クライアントの要望に応じたメンタルヘルスやエンゲージメント向上をテーマにした、オーダーメイドの研修事業です。
2025年10月には、既存サービスの知見をもとにした中間管理職を対象とした『ラポトレ!』をローンチ。これまでの公認心理師・臨床心理士との1on1プログラムと、24時間利用できるAIチャットを組み合わせた内容で、同社のこれまでの知見や思いが詰まったサービスとなっています。
【同社におけるローンチサービスはこちら▼】
- 管理者向けプログラム:『ラポトレ!』
- 妊活サポート:『妊活サポートサービス』
同級生の再会 ― 起業の原点
会社が生まれた「原点」について、皆様それぞれの視点からお聞かせいただけますでしょうか?
鶴田様▼
私は元々弁護士なのですが、コロナ禍の時期に業務量の増加などが重なり、メンタル不調に陥った経験があります。医療の力で回復はできましたが、誰もが適切なケアを受けられるわけではない現実に直面し、「同じように苦しむ人を一人でも減らしたい」という思いを強く抱くようになりました。
ただ、私は医学や心理学の専門家ではないため、具体的な解決策が思い描けずにいたとき、中学・高校の同級生であり、当時東で母子保健を研究していた伊角と再会する機会に恵まれました。
その後、伊角の研究仲間である土井とも意気投合し、メンタルケアをテーマに3人で起業しないか?という話になりました。
伊角様▼
鶴田と私の再会のきっかけは、鶴田がFacebookに投稿した1件のポストでした。そこには、「メンタルヘルス関係について、聞きたいことがある」と記載されており、周囲の専門家を紹介できるかと思って返信したことから私たちの交流が再開しました。
その後の鶴田との会話の中で、コロナ禍でメンタル不調を経験した鶴田の思いや信念に共感し、自分にできることはないかと考えました。
その再会が大きなきっかけになったのですね。伊角様、土井様は当時、どのような課題意識をお持ちだったのでしょうか?
伊角様▼
私は母子保健を専門に研究しており、共同研究者でもある土井と一緒に、メンタルケアが必要な方に対して、オンラインで公認心理師・臨床心理士が直接サポートする方法を模索していました。研究者として、より直接的に社会の役に立つ方法はないかと考えていたのです。
土井様▼
私も公認心理師・臨床心理士として、特に医療機関では、すでに不調に陥ってしまった人しか関われない「待ちの姿勢」に歯がゆさを感じていました。カウンセリングでは「もっと早く出会えていれば…」と感じるケースが多く、不調に陥る前の「予防的介入」の必要性を痛感していました。
皆様それぞれの立場から同じ課題意識を持たれていたのですね
鶴田様▼
3人の共通していた課題は、メンタル不調の「兆し」が表れても、本人や周りが見過ごしてしまい、それが原因で心の安定を大きく崩してしまう人がとても多い、ということでした。決定的な不調に陥る前に、誰もが気軽に適切なケアを受けられるサービスを開発したいという思いが一致し、BANSO-COの起業へと繋がりました。
実証実験で見えた理想と現実 ― 仮説検証から得た「学び」
最初のサービスはどのように生まれたのでしょうか?
鶴田様▼
当初は、企業や自治体を顧客(BtoB)として、個人向けの無料オンラインカウンセリングサービスを想定していました。しかし、いざトライアル版を展開してみると、無料の間は使われてもその先が続かない。「話して良かった」とは言われるものの、利用者の多くの方々から「有料でもまた使いたい」というほどの熱量は感じられませんでした。普通のオンラインカウンセリングでは、わざわざ予約し、かつ有償サービスに相談したいというニーズはそう強くないのだと気づかされました。
その気づきから、次のアクションとして「TAMA INNOVATION ECOSYSTEM」のプロジェクトに参加されたのですね
鶴田様▼
最初のトライアルで「ただ待っているだけでは、本当にケアが必要な人に届かない」と分かり、もっと利用へのハードルを下げる新しい「入口」が必要だと考えました。そこで、多くの方が日常的に利用するマッサージや整体のような「身体的なケア」を入口にすれば、心のケアへの抵抗感も薄れるのではないかという仮説を立て、それを検証するためにプロジェクトへの参加を決めました。
実証実験では、具体的にどのような取り組みをされたのですか?
伊角様▼
3か月という短期間で、多摩地域の子育て世代を対象に実証実験を行いました。具体的には〈理学療法士による体の使い方(オンライン)セミナー〉〈理学療法士による個別施術〉〈心理士オンライン相談〉〈NPO主催の自然体験〉という4つのプログラムを自由に組み合わせられる形で提供し、計26名の方にお申し込みいただきました。
そのうち、実際にいずれかのサービスを利用されたのは12名で、身体のセミナーを入口に公認心理師・臨床心理士との面談へ進んだ方は利用者の約3割にのぼりました。通常の企業向けオンライン相談窓口の利用率が4~5%程度であることを考えると、間口を広げる一定の効果は実感できました。
実証実験から、得られた課題について教えてください
土井様▼
身体的ケアによって間口は広がった一方で、子育て世代の方々の「自分のケアは後回し」という現実や、特に子育て世代はすでに自治体から多くの無料サービスの提供を受けており、有料サービスを利用することへの抵抗感が根強いという課題に直面しました。このとき、身体的ケアからメンタルヘルスケアへ繋げる難しさを感じました。
鶴田様▼
ビジネスの視点では、SNS広告などの広告費とサービス利用者間の費用対効果が芳しくなく、結果的にBtoCでは利益が上がらないということがわかりました。これは、私たちにとって今後の会社の方向性や戦略を考えるにあたって欠かせない、重要なデータです。これらの検証の結果、BtoCでのスケールは困難と判断し、BtoB向けのサービスへと舵を切る決意をしました。
管理職研修へのピボット ― 「個人の自主性」に頼らない仕組みへ
BtoCからBtoBへと転換された後、どのようなサービスを構想されたのでしょうか?
鶴田様▼
まず、企業にメンタルヘルスケアを提案する中で、多くの企業が「メンタルケア自体は重要だが、予防に大きな予算は割きづらい」という本音があることが分かりました。そこで、企業の方々にとってもメリットを感じて頂きやすい「従業員のエンゲージメント向上」や「職場の心理的安全性」にフォーカスした企業向けプログラムを提案しました。しかし、こちらもサービス設計が複雑で、企業側にご納得頂けるまで時間がかかるという課題が残りました。
その課題を踏まえ、10月にリリースした新サービスについて教えてください!
鶴田様▼
BtoBサービスでの反省を踏まえ、私たちが着目したのは「中間管理職」です。ある調査では、管理職のエンゲージメントが職場全体に大きく影響することが示されています。そこで、「人間関係を良くするスキル」を管理職研修として提供し、公認心理師・臨床心理士と1on1で実践的に学ぶ1年プログラムにサービスを絞り込みました。
本プログラム最大の特徴は、研修と位置づけることで利用者の自主性に頼らず受講を義務付けられる点、それにより、受講者は無意識のうちに自身のメンタルケアを実践できるようになるということです。
大学の知とネットワーク ― エビデンスが駆動力
アカデミアと連携し続けることで得られる強みやまた産学連携に対する追い風は感じましたか?
土井様▼
私たちは予防を扱う以上、エビデンスベースで事業を進めることを何よりも大事にしています。大学との連携を続けることで、効果検証のデータを即座に取り、その科学的根拠に基づいてサービスの質を高めていける。これがアカデミアと連携する最大の強みだと思います。また、大学側でも大学発ベンチャー向けの支援制度が年々充実しているのも追い風だと感じました。
伊角様▼
大学同士や大学と企業をつなぐ産学連携ネットワークも非常に大きな力になります。実際、私たちも企業とのマッチングイベントに参加したほか、学内で企業ニーズをヒアリングする機会も得られたなど、立ち上げ時には様々なネットワークに助けられました。
メンタルヘルスケアの未来 ― 公認心理師・臨床心理士によるケアをLINE感覚に
今後の展望についてお聞かせください
鶴田様▼
創業時からの目標は「メンタルヘルスで苦しむ人を一人も生まない」こと。そのために心理士によるケアをLINEで友人に声をかけるくらいと同じくらい気軽にしたいと考えています。それに向けて、まずは8月リリースの管理職研修をきっかけに、企業内で自分の課題について公認心理師・臨床心理士と話すことが当たり前の文化となるような仕組みをつくり、その重要性を広めていくつもりです。
ハードルを下げるという意味では、24時間対応のAIチャットサービスの活用も有効だと考えていますし、すべての人が適切なメンタルヘルスケアを受けられるために様々な施策を考えています。
最後に、読者の皆さんへメッセージをお願いします!
伊角様▼
研究で得た知見を実装化できる機会は、そう多くはないと思います。産学連携は研究者だけでは到達できない発想や視点をもらえ、研究成果を世の中の役に立つサービスへ変換できるチャンスだと思っています。
土井様▼
研究者の多くは研究成果をどうマネタイズしながら実装するかまでは学んでいないことが多いですが、その機会が得られるのは大きいですね。また、連携の過程でいわゆる専門家ではない方々とお話する機会が多くなるのですが、逆にそれが功を奏して、今まで思いつかなかった新しいアイデアを得られるほか、事業のブラッシュアップに繋がるなど、とても有益だと感じています。
鶴田様▼
企業側の視点に立つと、想いがあっても知見や技術が伴わないことってあると思います。その点、アカデミアとの連携は専門性や知見、ネットワークという意味でも大きな広がりを得ることができます。
一方、研究者側の視点と企業側の視点が乖離することもあるので、企業側には、研究者のモチベーションを尊重しつつ、プロジェクト全体を成功に導くための丁寧な調整能力が求められると感じています。それに取り組むことで、自分自身の成長にも繋がりますし、何より事業の加速に繋がる点で取り組む意義は大いにあると思います。
まとめ
実証実験で得た「届かない」という学びを元に、メンタルヘルスケアを「管理職のスキル研修」という企業が投資しやすい形へ再定義した、そのしなやかな姿勢。それこそが、研究成果とビジネスをつなぎ、社会実装を成功に導く確かな道筋の一つと言えるでしょう。同社のたゆまぬ挑戦により、メンタル不調を“兆し”でとらえ、適切なケアへつなぐ選択肢が今広がりつつあります。
取材企業:株式会社BANSO-CO
- 法人名:株式会社BANSO-CO
- 会社ホームページ:https://www.banso-co.co.jp/
- 代表取締役:鶴田 桂子
- 設立日:2021年7月
- 主な事業:オンラインカウンセリング事業、オンラインコーチング事業、メンタルケアに関する事業、人材の育成、職業適性判断及び能力開発に関する、研究・分析、教育業務ほか
「多摩イノベーションエコシステム促進事業」について
東京都では、多摩地域に集積している技術力の高い中小企業や大学・研究機関などが多様な主体と交流・連携し、イノベーションを起こし続ける好循環(エコシステム)をつくる取組を進めています。
▶ WEBサイト:多摩イノベーションエコシステム促進事業