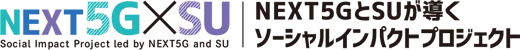遠隔操作で顧客支援サービスを行う、avatarin(アバターイン)株式会社(以下、avatarin)のアバターロボット「newme(ニューミー)」をローカル5GとDASの環境下で使い、遠隔による区民サービスの有効性や技術面を検証する実証実験が2024年9~12月に大田区役所本庁舎にて行われました。これは、東京都「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」に開発プロモーターとして採択された株式会社キャンパスクリエイトの支援のもとで行われたものです。(実証の概要については、第1回「avatarinに聞く、実証の概要と結果、今後の展望」をご覧ください。)
そこで4回に分けて、関係した4社にそれぞれの立場でお話を伺っていきます。第3回は、本実証に際し、共同研究として遠隔接客業務に関する調査研究を行った、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研) 人間社会拡張研究部門 ソシオデジタルサービスシステム研究グループ 研究グループ長の渡辺健太郎さんに、本実証に参画された背景や成果、今後のnewmeの可能性について伺いました。
3ヵ月の長期にわたるnewmeの実証で、接客の試行錯誤を調査
―まず、産総研として本実証に取り組まれた背景や理由について、お聞かせください。
渡辺:私は産総研の人間拡張研究センター(当時)に所属して、人間のスキルややりがいなどをいかに拡張し、楽しく働ける、イキイキと暮らせるような技術開発によってそれをうまく世の中に当てはめていくかを研究対象としています。そうして着想した「拡張テレワーク」という概念について、2020年、コロナ禍のさなかに当センターが発信した白書に記載しました。
Zoomなどのオンライン会議ツールを用いたテレワークが定着しつつあるなかで、人とのコミュニケーションやリアルな体験が難しくなったというのが課題意識として出てきており、私たちが研究している「人間拡張技術」による、これまでにない形のテレワークを構想したのです。以来、この「拡張テレワーク」という概念のもと、さまざまな共同研究を行ってきましたが、なかでもavatarin社のnewmeは、対面の接客を遠隔でできる点で、私たちが提唱した概念に合致するテクノロジーであると非常に関心を持っていました。
今回の大田区における実証事業については、3ヵ月という長期間をもって実証されると聞き、どのようなインパクトがでてくるのかと興味をもち、参加させてもらいました。また、それを公的セクターにおける接客で行えるというのも魅力でした。
―実際に本実証で取り組まれたのは、どのようなことでしたか?
渡辺:長期間なので、オペレーターに定点でインタビューを行い、接客の体験ややり方がどういう風に変容していったかを聞き、把握していきました。これまでも短期に導入するケースでの聞き取り機会はありましたが、今回はやはり3ヵ月にもわたるため、状況の変化があり、オペレーター側でも接客の改善についていろいろな形で取り組んでいたのが分かりました。
どんな仕事でもある種の習熟過程があるものですが、特にアバターロボットを使っての接客はまだ事例が少ないなかで、オペレーター自身はもともと接客のプロではありますが、いろいろ試行錯誤してロボットに合わせて接客スタイルが作られていく過程を把握でき、 非常に興味深かったです。
―具体的には、どのような変化があったのですか?
渡辺:サービスのなかでデジタル技術を使いながら、どういう風に新しい接客のあり方ができるか、サービスをどういう風に運営していくとよいか、というサービス工学の研究では、顧客と従業員の関係性を「価値共創する関係性」であるといいます。たとえば私が顧客だとすると、質問されたことに答えないと価値が生まれないように、従業員だけでなく顧客も何かをしないと価値が生まれないということがあるので、相互に関係性を作っていくことが大事なのです。
そして実際にその価値共創を起こそうとすると、顧客にこの体験自体のプロセスを理解してもらう必要があるのですが、新しい技術が入ってきたときにはそれがネックになりやすいもの。通常の受付なら従業員は待っていれば顧客が自ずといらして、それに対応しますが、今回の実証でいえば、顧客はまだnewmeを認識しておらず、自分がどうすればよいのか分かりません。そこで従業員の方から顧客にアプローチして、顧客の課題感に寄り添っていくように変わっていかねばなりません。そうした変化が重要だと思いました。
実証期間が3ヵ月あると同じ来庁者に複数回対応することもあったそうで、そのように顧客の側でもnewmeに関する認識が進み、自分からアプローチできる顧客が増えていくと、newme活用の可能性が広がります。そこに至るまではオペレーターとしてこの認識を作っていきながら、やり取りのあり様が変容していき、新しい技術を一緒になって使いこなしていくようになるのが興味深かったです。
接客業務が時間・場所の制約から自由になり、スキルの拡張へ
―そのほか、何か発見はありましたか?
渡辺:newmeでは画面の向こうにいるのは人だというのも、非常に大事だったと思います。国際的に近年ロボットを使ったサービスに関する研究が増えていますが、それは日本でも数々の実証がされてきた、自動で動くロボットによる接客が盛り上がっているのです。そのなかで、newmeのような人がオペレートするアバターロボットの研究を実証的に取り組むのは日本以外ではあまり聞かず、世界でも先進的な取り組みだと思います。
もう1つ、接客というのはその時間・その場所にいないと基本的には成立しないサービスで、そこに価値があります。しかし他の業態に比べ、1人の人がその場にいる人に対してしか接客できないため、生産性を向上させるのは難しかった。それがアバターロボットを使えば、いま東京で接客した人が次の瞬間には仙台で接客することができるわけです。これは対人接客という歴史あるサービスにおけるドラスティックな変化で、大きな可能性を感じます。従来、接客スキルがあって対面で就業している人がいろいろな場所で仕事ができるようになると、さらに大きな価値が生まれてくるでしょう。そのスキルをもって遠隔化することで、スキルを拡張できるという意味で、私たちが取り組む人間拡張的な観点から、非常に可能性を感じる技術分野なのです。
―接客では、人が対応する画面型のソリューションもありますが、動けるという特徴のあるnewmeならではのことはあるでしょうか?
渡辺:存在がある、というところに意味があります。技術研究用語で「身体性」という言い方をしますが、そこに存在していることというのは現実で暮らしているうえでは大きな意味があることです。対象に対して愛着を持ったり、一緒にコミュニケーションする感じがあったり、遠隔でもその人に寄り添って動いたりできるというのは、同じ遠隔でも単に画面越しに話している以上に意味や情報を伝えることができます。今回、ローカル5Gを活用することで遅延なく自然なコミュニケーションを可能としていましたが、通信が安定していること自体が遠隔からの接客サービス品質の向上にも繋がります。そこから得られる価値も大きく、大いに可能性があるといえます。
リスク管理とルールメイク、サービス全体のデザインが、普及・浸透のカギ
―区役所以外でnewmeの設置を想像した場合、どのような場所の案内・接客業務に応用できそうだと感じられましたか?
渡辺:今回は目的地への誘導が大きな役割でしたので、今後も観光ガイドや駅など、公共交通機関での案内などが、直近ではあると思います。さらにnewmeは動くこと以外に、口頭での情報・知識伝達ができるという特徴のある技術ですので、そうした用途に該当するような、手を貸さなくても大丈夫な接客サービスであれば、いろいろ使っていける余地があるでしょう。
また、すでにavatarin社で取り組まれていますが、従業員がロボットに入って活用するだけでなく、顧客がロボットに入って店舗や施設で新しい体験をすることもできます。こうした活用の方向性はすでに研究的にも整理されてきていますが、そのように両者が使う形での運用のし方もこれから出てくると期待しています。
―利用者がロボットに入るときに、何か課題はありますか?
渡辺:オペレーターは組織として訓練や教育が可能ですが、顧客はそこまで管理できないので、意図しない用途や危険な行動が起こりかねません。そのリスク管理は課題になってくるでしょう。それはロボットの安全面の話でもあり、使い方のルールメイクという話でもあります。このリスク管理とルールメイクがきちんとできていけば、そこも可能性が広がると思います。
また、サービスの研究では「サービスシステム」という言い方をしますが、テクノロジーを入れればうまく行くとは必ずしも限りません。それを入れることによって顧客や従業員に対してどういう新しい体験が生まれるのか。その体験を構成する要素というのは技術だけでなく、接客のプロセスや、現地でどういう風に振舞うか、そこにいる人がどういう風にナビゲートしてあげればいいかなど、全体をデザインすることが重要。私の研究の立場でも、このようにサービス全体をシステムとして適切にデザインすることが、テクノロジーの社会における価値化には大事だと考えています。
―最後に、newmeへの今後の期待をお聞かせください。
渡辺:少子高齢化の進む日本において、公共も含めた必要なサービスを持続していくために、newmeに可能性を感じています。特に大事なのは、単に自動化するだけではないという点です。そこに人がいて、その人が自分のスキルをうまく活用しながら、役割を持って社会のなかで働ける。しかも時間・空間にとらわれず働けることで、その人自身の生産性も高めながら、社会のなかでさまざまな人がサポートし合っていく。そうした社会が実現するための、可能性あるテクノロジーだといえます。引き続き、多くの人がこうしたことを体験しながら、社会においてうまく活用されていくことを期待しています。
(第3回終わり)
【avatarinが大田区役所で「ローカル5G×DAS×アバターロボット」による遠隔区民サービスの有効性を検証 他の連携記事】
(第1回) https://www.campuscreate.com/next5g/407/
~avatarinに聞く、実証の概要と結果、今後の展望~
(第2回) https://www.campuscreate.com/next5g/414/
~大田区役所に聞く、行政における実証の意義や成果、アバターロボットの可能性~
(第4回) https://www.campuscreate.com/next5g/421/
~電気通信大学に聞く、実証フィールドにおけるキャリア通信環境とアバターロボットの可能性~