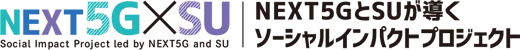遠隔操作で顧客支援サービスを行う、avatarin(アバターイン)株式会社(以下、avatarin)のアバターロボット「newme(ニューミー)」をローカル5GとDASの環境下で使い、遠隔による区民サービスの有効性や技術面を検証する実証実験が2024年9~12月に大田区役所本庁舎にて行われました。これは、東京都「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」に開発プロモーターとして採択された株式会社キャンパスクリエイトの支援のもとで行われたものです。(実証の概要については、第1回「avatarinに聞く、実証の概要と結果、今後の展望」をご覧ください。)
そこで4回に分けて、関係した4社にそれぞれの立場でお話を伺っていきます。第2回は、行政におけるこの実証実験の意義や成果、newmeに感じた可能性について、大田区産業経済部 イノベーション事業担当課長 八木弘樹さんに伺いました。
大田区初。本庁舎におけるスタートアップによる大規模な実証実験
―まず、大田区が今回この実証実験に取り組んだ理由をお聞かせください。
八木課長:働き手不足が深刻化するなか、大田区でも「ずっと住み続けたい大田区」の実現を目指し、区民サービスを維持、向上させていくために行政DXに取り組んでいます。そして私の部署では、羽田イノベーションシティ(HICity)のプロジェクトを推進し、先端的なソリューションを開発されている皆さんと連携して地域課題解決につなげようというテーマにずっと取り組んできました。
また、大田区はavatarin社と2020年12月に「デジタルトランスフォーメーションにより誰もが社会参画可能な地域社会の実現に向けた連携に関する基本協定」を締結しました。その協定に基づき、同社のnewmeの活用に関して、HICity内の「PiO PARK(ピオパーク)」で実証実験を重ねてもらったのです。大田区としてはここでの成果を社会実装し、区民がメリットを感じられるような形でサービス向上につなげたいという思いがあったわけで、同社より2024年度には、区役所本庁舎での区民サービスの提供において一歩進んだ実証実験として実施したいと提案があり、区の思いとも合致して今回、実現に至ったのです。
―区役所で、しかも本庁舎での実証実験となると、調整などが難しかったのではないですか?
八木課長:区民サービスの提供における実証実験ということで、地域庁舎や特別出張所などもありますが、本庁舎が最も来庁者が多く、いろいろな方が見えるので、実験する場として相応しいと判断しました。調整については、ロボットが来庁者とぶつかったりはしないか、サービス面で何かクレームにつながるようなことが生じないだろうかなどを検討し、現場を抱える各所管と確認を重ねてクリアしていきました。
そもそも本庁舎内でスタートアップが大規模な実証実験を行うのは、大田区でも初の取り組みです。当部署として大きなチャレンジでした。
―そうして実証実験に取り組んでみて、区役所の案内業務にどのような点が役立つと感じられましたか?
八木課長:安心して、きちんと目的地にたどり着きたいという目的が達成できれば、newmeでも十分代替可能だと証明できたと考えています。特にnewmeは画面に顔が映るので、人とのリアルなコミュニケーションに近い形で対応できるのが、利用者の安心感につながったのでしょう。ロボットであっても音声のみで遠隔で通話するような製品もありますが、サービスを受ける方の立場になれば、顔が見えるのは重要だと思いました。それもあってか、若い層に限らず、シニアも違和感なく話をされていたのが印象的です。
これを助けたのが、移動できるというnewmeならではの特徴でしょう。固定式のパネルでお声がけしても、来てもらったり気づいてもらう必要がありますが、newmeならオペレータ側から向こうの様子が分かるので、何か悩んでいたり迷っていそうな方を自ら発見してアプローチができます。ソリューションとしての大きな強みですね。
3ヶ月間という長期の実証で、「動くアバターロボットnewme」を多くの人が認識
―newmeでは行動データなどを分析もできます。これも案内業務に役立つでしょうか?
八木課長:そうですね。区役所としても接遇マニュアルは作っていますが、暗黙知的なものは伝わりにくいので、データが蓄積されて改善につながるとよいですね。avatarin社ではAIに学習させるためのデータも作られているので、そうしたものも共有できればサービスの向上や適切なご案内にも非常に役立つでしょう。
―区役所内で今後、どのような活用の仕方が考えられるでしょうか?
八木課長:遠隔から支障なく業務が行えたので、今回はnewmeを操作するのは事業所のスタッフでしたが、今後はこれをツールとして行政職員が操作して、遠隔から効率的にサービスを提供することも考えられます。たとえば、地域庁舎や特別出張所に専門的知識や対応が必要となる来庁者がいらした場合に、今は電話ベースで職員がやり取りして、聞いた話を伝えたり、直接電話口に出ていただいたりしています。それをnewmeが出張所などにも配置されていれば、必要に応じて専門的知見を持つ職員がnewmeを通じて直接、その来庁者に対応することができます。これは区民サービスの向上になりますし、職員が場所を移動する時間的コストも解消できます。
このように、newmeが各拠点にあって、さまざまな職員が利用できるようになっていれば、時間や場所に縛られない仕事の仕方ができるようになるでしょう。これが浸透すれば、職員採用において障がい者雇用もより推進できる。そうした面でも有効だと感じます。
―これまでの案内窓口の省力化や新しい使い方も生まれてきそうですね。
八木課長:そのとおりでコミュニケーションの幅が広がります。また、newmeの良い点は、移動ができることです。通信基盤が整う前提ではありますが、エレベーターも自由に乗って移動できれば、執務室から会議室に自分で行くこともできますね。
その点で、今回の実証で複数階にわたってのサービス提供も確認できているのは心強いです。
―そのほかに、今回の実証実験で何か発見はありましたか?
八木課長:区民にとっては、newmeのような見慣れないものでも案外、受け入れていただけるのだということですね。シニアもむしろ興味や関心を持ってくれていたのが印象的でした。
また、3ヵ月にわたって実証を行ったことで、区民にも職員にも、多くの人にnewmeというものを知ってもらえ、理解が進んだと思います。現物が動き、案内業務を行っている様子を見ると、自分ごととしてイメージしやすいでしょう。今後の活用について、実証後に職員アンケートも実施したのですが、いろいろアイデアが寄せられたので、活かしていきたいです。当部署としては実証で終わらせず、具体的に区のなかでどういう活用ができるか、継続的に議論を巻き起こし、各所管の活用をコーディネートしていかねばと考えています。
区役所がとなって、地域に価値を広めていく
―区役所以外でnewmeの設置を想像した場合も可能性を感じられますか?
八木課長:newmeに限りませんが、SDGsの観点で持続可能な社会を作っていこうと考えたときには、行政だけでなく、地域のさまざまなプレイヤーや企業などと面として取り組んでいく必要があると考えています。そのうえで、newmeのようなものをいかに区役所がファーストペンギンとなって、周りに安心感を持って広げていけるか。有効性を伝え、それぞれのプレイヤーの事業のなかでツールとして取り込んでいただくか。そうした広がりを持たせるのが、区役所の役目だと思っています。newmeでいえば、社会全体の限られた人材リソースをエリアで最大限有効活用していくのに、大いに役立ちますね。
―大田区役所として、さまざまなスタートアップとのお付き合いがあり、地場産業や商店街など、地域のステークホルダーも数あるなかで、うまくコーディネートしていくことが大事なのですね。
八木課長:今われわれがやらねばならないのは、そうした社会課題を解決したいという意欲あるスタートアップの皆さんに活躍の場をどんどん提供し、本当によいものは発展させ、社会に浸透させていっていただく。そこをしっかり応援したいのです。
2024年度より「大田区実証実験促進事業」として、そうした地域に貢献できるようなソリューションの実証実験について、当部署のほうで行政現場のフィールドをきちんと提供しながら伴走していく仕組みを作っています。このようにサポートしていき、面として取り組めるよう横展開していきたいですね。
さらに2025年度以降、注力していきたいのは、地場産業との連携の強化です。区内企業が有する匠の技術に、スタートアップのような新しいアイデアや柔軟な発想が掛け合わされることで、新しい価値の創造につなげていきたいです。
大田区様のご意向となりますので、最初の記載のままとさせていただきます。
―最後に、newmeへの今後の期待をお聞かせください。
八木課長:本当に社会を変えられるようなインパクトのあるソリューションだと捉えています。大田区や民間事業者との実証の成果をふまえて、引き続き完成度の高いソリューションに磨き上げていってほしいですね。
また、これを活用する側として、従来の概念で活用の場を考えていてはなかなか広がらない部分があると思うので、固定概念を全て取り払い、柔軟な発想でいかにこのソリューションの活用可能性を自分たちで考えられるかが重要になると思います。官民問わず、皆で考え、議論して新たな価値を生み出していけるような社会にしていきたいです。
第2回終わり
【avatarinが大田区役所で「ローカル5G×DAS×アバターロボット」による遠隔区民サービスの有効性を検証 他の連携記事】
(第1回) https://www.campuscreate.com/next5g/407/
~avatarinに聞く、実証の概要と結果、今後の展望~
(第3回) https://www.campuscreate.com/next5g/419/
~産業技術総合研究所(産総研)に聞く、遠隔接客業務における実証の意義や成果、newmeの可能性~
(第4回) https://www.campuscreate.com/next5g/421/
~電気通信大学に聞く、実証フィールドにおけるキャリア通信環境とアバターロボットの可能性~